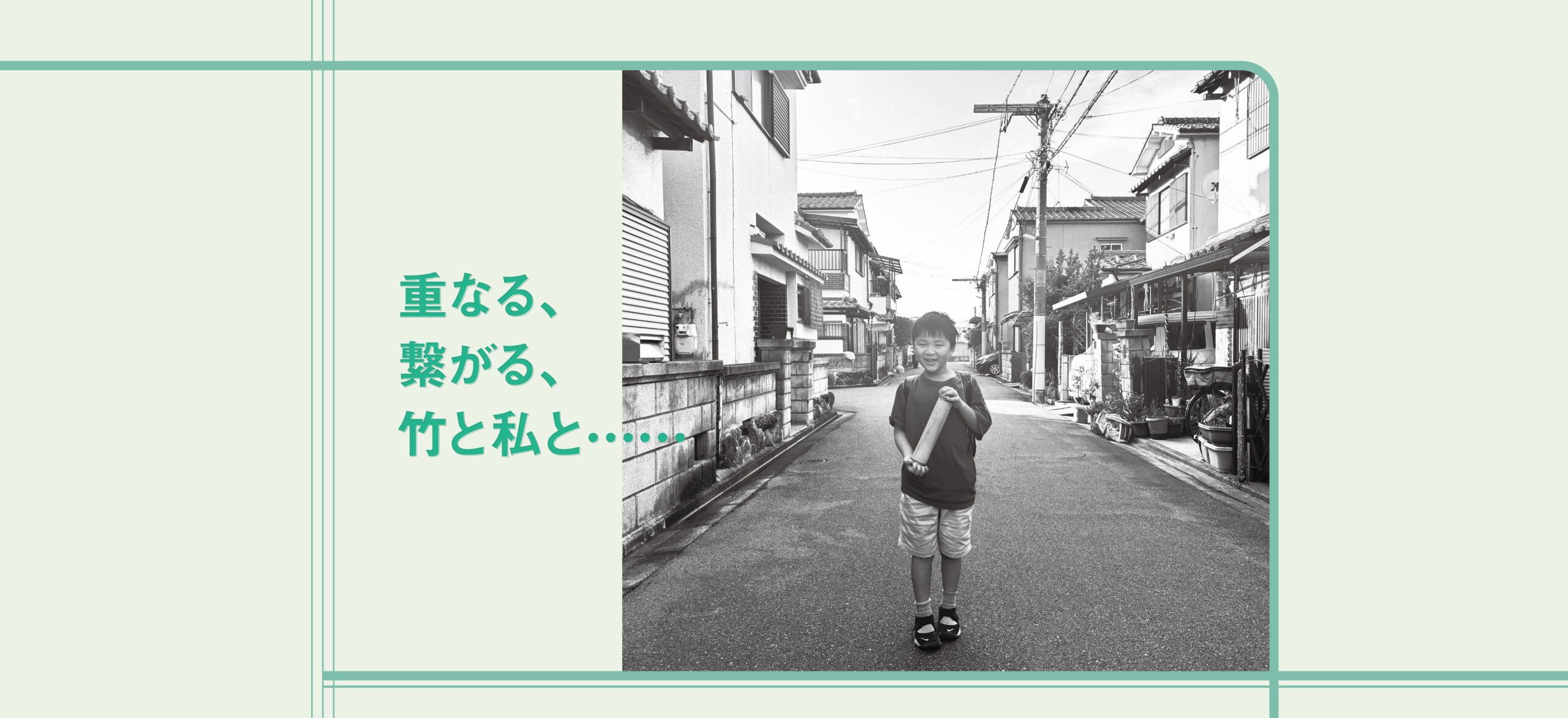夏休み、息子たちには小学校から貯金箱を工作する宿題が出た。
「父ちゃんとじいじの家でやるから大丈夫」と笑顔のヒカル。
本当か……遊び呆けてやらないのではないのか。
大阪よりお店もないし材料や道具を買うのも大変じゃないのか。
そんな私の心配をよそにヒカルは兄と父と和歌山に旅立った。
便利。だけど、ボール遊びをする場所もない日常で。
私の住む街は、家から5分も自転車を走らせれば5つのスーパーがある。
夜に突然、子どもから明日の学校で必要なものを買ってと言われても手に入る。子育て中の我が家には便利で住みやすい街である。
しかし子どもにとってはどうか。小学校区内には海も山もない。公園には多くの注意事項が掲げられた看板があり、子どもたちは外で遊ぶのにも窮屈さを感じている。
「ママ、ボールで遊べるところがない」と話す息子。
親としては「約束守って遊んでや」としか言えない。
なんとも歯がゆい会話が日常的に行われている。
こう言った時の息子たちの不服そうな顔に、いつも親としての不甲斐なさを感じる。
そんな日常を送る我が家にとって、夫の実家がある和歌山は息子たちの思いっきり遊びたい気持ちを満たしてくれる大切な場所である。
小学校から大阪で暮らす私と18歳まで和歌山で過ごした夫では幼少期の過ごし方が本当に違う。家で本を読むことが好きだった私とは違い、紀伊山地の山、太平洋の海に囲まれて育った夫。いつも夫の幼少期の話を聞くと、大自然で遊んだ風景が想像できてわくわくするのだ。
おおらかな祖父母と過ごす。和歌山への帰省
待ちに待ったお盆休み、夫と子どもたちは3人で祖父宅のある和歌山に帰省した。
私は仕事のために後で合流する予定。少し寂しい気持ちもあるが、口うるさい母親のもとを離れ、おおらかな祖父母と和歌山の自然に囲まれ、のびのびと過ごしている子どもたちの姿を想像すると嬉しくなる。そんなことを思いながら合流する日を楽しみに仕事をこなした。
しかし、結局、南海トラフ地震臨時情報発表のため特急列車が運休となり帰省できず、私は大阪で一人留守番となった。
「色塗りとか飾ったりせえへんの?」「これでええねん!」
1週間ぶりに帰ってきた3人。全身真っ黒に日焼けし、満面の笑みで帰宅したヒカルは「ちゃんと貯金箱作ってきたで」と勢いよく話した。その手には一節の竹が握られている。
よくよく見ると、硬貨の入る穴があいたそれが貯金箱であった。あまりに簡素な作品に私は「色塗りとか飾ったりせえへんの?」と聞いてみた。ヒカルは「これでええねん!」とこれまた潔い返事。あまりにもすがすがしい返事に、妙に説得力を感じて笑ってしまった。
しかし青々とした竹の貯金箱を手に取り、その気持ちは一変した。すぅっとまっすぐ立つ姿、表面は単一な色ではなく、成長過程でついたであろう緑・黒・白がまだらに入り乱れている。一見つるっとしているかと思った質感は、触ると少し節があり小さな凸凹が感じられる。長い間、山奥で風に揺られ、雨に当たり、太陽の恵みを受けて成長してきたのを感じた。
気が付くと、自然と和室に足が向いていた。そして和室にその貯金箱を置いてみた。なんという存在感だろう。祖父の山に夫と入り、選りすぐった竹を持ち帰り、庭でああだこうだと話ながら作る夫とヒカルの姿が浮かんだ。切り出した断面は生成色で少し斜めに切り落とされ、ざらざらとしている。これはヒカルが初めてのこぎりを使う喜びに満ち溢れ、力いっぱい動かしたから下書きどおりいかんかったんやろなぁ。竹を押さえる夫はヒカルの成長を感じながらも、支える自分の指が切り落とされないかヒヤヒヤしたやろなぁ。
そんな場面が浮かんだ途端、ヒカルの言う通り、この貯金箱は十分に完成されたものであったと腑に落ちた。竹の物語をヒカルが貯金箱にして紡いだのだ。私はとてもあたたかい気持ちになった。
「竹を筋に沿ってすぅっと切り裂くときは、潔い感覚を得ます」(四代目田辺竹雲斎氏)
竹はさまざまな生活用品や道具として私たちの生活に入り込んでいる。また、生活道具だけでなく、その活用方法は建築や造形作品など多岐にわたっている。
大阪には千利休が大成させた茶の湯文化、近代の経済界や文人における煎茶文化があり、竹細工はその道具として存在した。そのような文化と共に堺市を中心とした大阪近代竹細工の文化が生まれ、今も伝統を受け継いで創作に取り組んでいる方がいる。四代田辺竹雲斎氏もその一人である。
先日、京都福寿園ギャラリーでの展覧会で話を聞く機会をいただいた。そこで私が貯金箱に抱いた気持ちを質問し、四代田辺竹雲斎氏の思う竹への印象を聞いた。「竹を筋に沿ってすぅっと切り裂くときは、潔い感覚を得ます。その他にも、作品を作る時は竹のしなやかさや硬さなど、たくさんの表情が伺えます。四代目として先代の竹雲斎の伝統的な流れをそのまま受け継ぐのでは自分らしさがない。自分らしい作品とは何かを深く考えました。そしてこれまでは作品の材料にはなり得なかった朽ちた竹を使った「朽竹」という作品ができあがったのです。伝統と革新、この二つがあってこそ、伝統は引き継がれていくのです」と教えてくださった。
多様な顔を持つ竹の話を聞き、創作において材料を扱う人と扱われるものという上下関係をもってそれぞれが存在するのではなく、生き物と生き物が対話や共演するような姿勢で向き合っていることが伝わった。また、同時に竹にとっても人が自然の一部であり、お互いがそれぞれの特性を生かし協働することで新しい作品が生まれるのだと気づいた。
私があの貯金箱と対峙した時に得た感覚と重なった。物言わぬ者へ向き合う心を知り、心が躍った。これまでの自分の経験や思い込みでヒカルに放ったあの時の言葉を思い出し、言語的な説明ですべてを理解しようとした自分のなんとも浅はかで、傲慢であったことか。
もの言わぬものと共存すること
物語には続きがある。
12月初旬にヒカルの敬愛する祖父が他界した。自宅近くの海にいつも通っていた祖父。葬儀の後に家族で海を見に行った。夕刻の海、空には彩雲が現れた。とても雄大で美しい景色であった。帰り道、いつも海で祖父と過ごしていた友人たちにも会い、在りし日の話を聞き、自分の目の前の風景にその姿が浮かんだ。さまざまな災害が危惧される地域でありながら、その自然と共存していた祖父。
自然はコントロールすることなんてできないから、日々対話し共生しようという姿勢でいると心地よいのだ。日々の生活で不安になることもある。でも自分も自然の一部であることを認識すると、なんだか心強い気持ちになった。これもヒカルがあの貯金箱を通して私に伝えてくれたことと同じであった。あの貯金箱はヒカルと父、そして祖父との大切な時間をこれからも語るかけがえのないものになった。
この日もヒカルは竹の貯金箱の様に潔い姿で、勢いよく学校へ駆け出した。
長い忌引き休暇明け、真っ白の宿題を持って登校しようとするヒカルは、私の心配をよそに「じいじが死んだせいで宿題できなかった!」と自分への罪の意識もなく、あっけらかんと話す。
いきなり天国で孫に宿題できなかった責任をなすりつけられて、ずっこけてる祖父を想像したら、笑ってしまった。
この日もヒカルは竹の貯金箱の様に潔い姿で、ランドセルを背負って勢いよく学校へ駆け出した。
その背中には、これからの未来を切り開く力強さを感じた。
こうして物語はまだまだ続いていくのだ。

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について
「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。